箱型のペンケースを使いましょう
子供の学校では、「ペンケースは箱型」と学校がルールを決めています。
ところが、子供たちの間で、「高学年になったらファスナー型を使っても良い」という空気が出来上がっているのです。
「いいのかな~、だめなのかな~、どっちかな~」と思いながらも、「学校のルール」を守らずに、ファスナー型を持ってくる子が多くいます。
そして、学校のルールを守らずにそのままファスナー型を使い続けている子も多くいます。
この「子供の実態に合わない、学校のルール」というものが、落とし穴の入口です。
ルールを与えられることにより、高学年になる子供は、それぞれが、多様な『考え方』をします。
分かりやすくするために、6つに絞って例を出します。

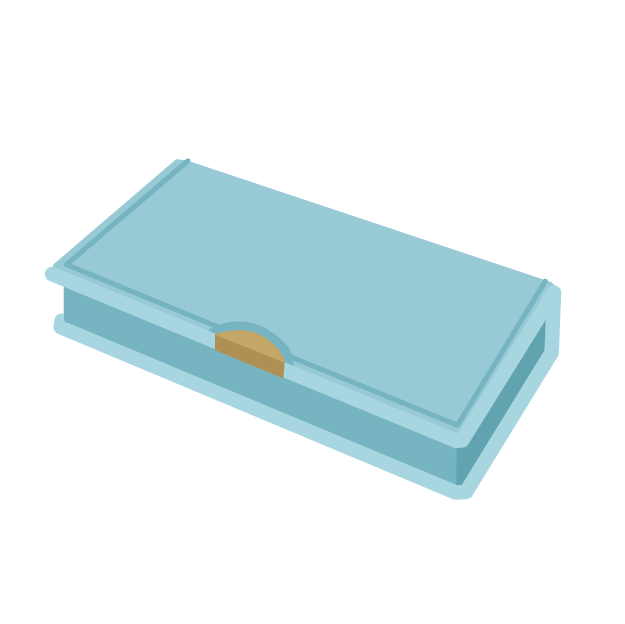
④ 本当は自分だってかわいいファスナー型を使いたいけど、学校がダメって決めてるよ… 大好きな先生を裏切りたくない。
⑤ 箱型だろうがファスナー型だろうが、どうでもいい! 黙ってルールに従っていればいいのに!
⑥ 何でルールを守らないの? ずるい! 私はちゃんと守っているのに! 先生に注意されなければ、ファスナー型にしてもいいとでも思っているの?
①②③ の『考え方』の人は、ファスナー型を使うという『行動』をします。
④⑤⑥の『考え方』の人は、箱型を使うという『行動』をします。
①~⑥ 、どの『考え方』が1番良いと思われますか?
・私は②だな
・そういえば、周りと合わせようとしたから、③に近いかな
・子供のときは④の考え方だったけど、今は①かな…
・自分の考え方は、この6個の例にはないな…
いろいろかもしれませんが、
私が聞いているのは、
「どの『考え方』が自分と近いですか?」
ということではなく、
「どの『考え方』が1番良いですか?」
ということです。
「ファスナー型を使う子供」
「箱型を使う子供」
この『行動』を見て、多くの親や先生はどうするかというと…
「ルールを守って偉いね」
と、④⑤⑥の『考え方』で箱型を使い続ける子供を褒めます。
ルールを守っている子供たち、我慢してがんばっているからでしょうね!
そうすると、どういうことが起こるかというと…
④⑤⑥の『考え方』をしている子供たちは、
「自分の『行動』や、自分の『考え方』が素晴らしい」
と、いつの間にか思い込むようになります。
だって、
「正しい『行動』だ」と褒められるのですから!
大人の決めたルールに従って、褒められるから、
「正しい『行動』で、正しい『考え方』だ」と思うのです
このことにより、
④⑤⑥の箱型を使う子供たち、
大人が決めたルールに従って「正しい『行動』」をする子供たち、
特に⑥の『考え方』をする子供は、
「正しくない『行動』」のファスナー型を持ってくる子供たちのことを、
「ルールを守らない『行動』をする、あなたたちは良くない」
と思うようになります。
すると…
①②③の子供たちの『考え方』のことも、
「正しくない『考え方』だ」
と思ってしまうのです!!!!
①②③は、
ルールを守らない『行動』をする『考え方』
だからです。
「褒められた自分の『行動』が素晴らしい」
と思うから、
「自分の『考え方』も素晴らしい」
「自分の『考え方』が 素晴らしい」
のだから、
「違う『考え方』は 認められない」
というように、つながっていきます。
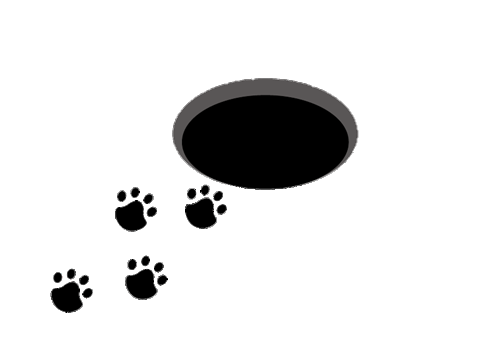
これが、大きな、大きな、落とし穴なのです!!!
先ほどの質問に戻ります。
「どの『考え方』が1番良いですか?」
私の考えは…
「これが1番、というのは、ない!」
「みんなちがって、みんないい」
「ただ単に、『考え方』が異なるだけのこと」
なぜなら、

私たちは、どのように考え、どのように感じても、
他人の迷惑にならない限り、【自由】だからです。
「ルールを守らない人を暴力で制裁してやる!」
「ファスナー型はルール違反だよ、って、あの子が何度も言ってウザいから、悪口をばらまいてやる!」
「ムカつくからファスナー型のペンケースを隠してやる!」
「あいつのペンケースを壊してしまえ!」
というような、
人の迷惑になる(他人の権利を侵害する)
『考え方』を表現しない限り、
どんな『考え方』をしても、私たちは【自由】
という【権利】があります。
内心の自由
私たちの心に制限はありません。
表現の自由
「他人の権利を侵害しない限り」という制限があります。
何でもかんでも表現して良い、というわけではないのです。
「自由に感じ、自由に考えて良い」という権利は、日本国憲法で保障されています。
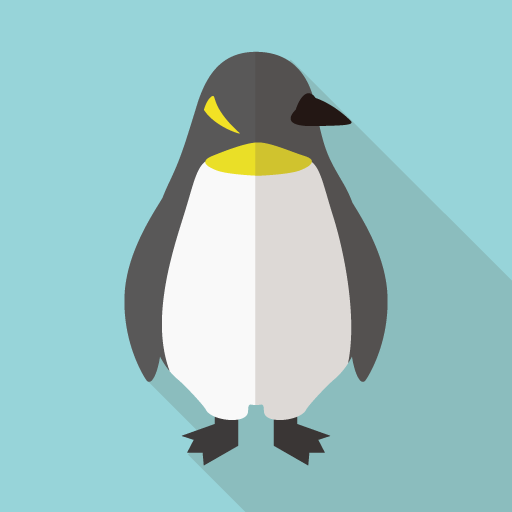
え? 何?
日本国憲法ですって?
難しいこと?
このように思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私たち日本人が、法律、ルールを決めるときには、この「憲法を守る」ということが大前提なのです。
権力から私たちを守るための【権利】が日本国憲法には記載されています。
・私たちの【自由】
・1 人 1 人の心が大切にされ、幸せになるための【権利】
これを保障している 憲法です。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
日本国憲法 第十二条
努力をし続けないと、自由の権利は奪われてしまうこともあるのですよ!!
自分たちで努力して守らないと、自由はなくなります!
ボーっと生きていると、いつの間にか、自由はなくなることもあります!
チコちゃんに叱られてからでは、遅いのです!
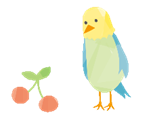
心で感じ、頭で考える。
1人1人、違う感じ方、違う考え方をします。
それなのに、なぜ、④⑤⑥の『考え方』をして、箱型の『行動』をする人が褒められるのでしょう?
「ルールを守っているから」ですよね。
だけど、この学校のルールは、大人が「正しい『行動』」と思っているルールなのです。
これは、子供の『心』『考え方』に寄り添ったルールになっていません。
「自分がこの素晴らしい教育のおかげで立派な大人になったのだから、同じように、自分が受けたこの素晴らしい教育を受けさせたい」という「こだわり」を持つ大人が、このルールを保持し、守り続けているのだと私は考えています。
この「こだわり」が、「変えること」について強く反発している、と私は推測しています。
なぜなら、
「自分が受けてきた教育が素晴らしいのに、変える必要はない」
「自分を立派に育て上げた教育方法であるから、これに従えない方が良くないのだ」
「自分が受けてきた立派な教育を変える、ということは、その教育が良くないことになってしまう」
と思うからです。
このような思想を持つ人は「子供に、正しい『行動』ができるようにさせたい」と、特に強く願っています。
「大人が正しいと考える『行動』」を、子供ができるようになれば良いのです
大人が決めたルール、大人が正しいと思っている『行動』を「はい、分かりました」って、ちゃんとやってくれる子、これが「いい子」なのです。
この ④⑤⑥の箱型を使う子供たちを褒めるという行為
実は、この行為、
「魂の殺人」です。
魂の殺人 ~ 親は子供に何をしたか ~
アリスミラー著
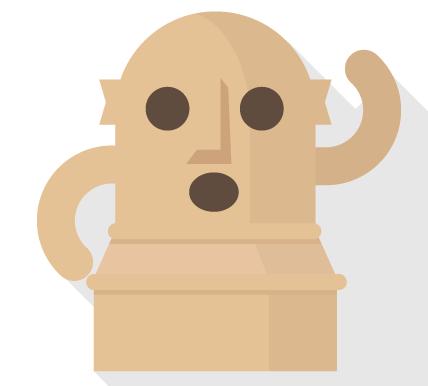
本のタイトルというのは、名言がとても多いです。
これからもいくつか引用しますが、タイトルが名言だと思うだけで、本そのものは読んでいません!
まさに、大人が望んでいる『行動』、大人が正しいと思っている『行動』を褒めることによって、子供の魂がつぶされているから、私はこう呼んでいます。
「我慢して頑張っているね!」
「我慢できない子もいるのに、あなたはえらい!」
これも、魂の殺人です。
大人が望む「我慢するという正しい『行動』」をさせるために、「我慢してえらいね!」と、その行動を褒めているのです。
このことにより、「我慢していない子は、正しくない『行動』をしている」ことになります。
だから、
「その『考え方』も正しくない」と思うようになり、「我慢しない『考え方』」は、つぶされます。
ただ、『考え方』が違うだけなのに!
「苦しいよ~」って言っているだけなのに!
言い換えれば、刷り込みです。
大人が子供に「大人が思う正しい『行動』」をさせるために、「我慢するのが良いこと」と刷り込んでいるのです。
①②③の子供たちの『行動』
これが、学校が決めたルールと合っていないだけのことです。
本当は、いろいろな『考え方』は認められてもいいはずですよね?
だって、
どのように考えても、私たちは【自由】なのですから!!
【自由】であることは、大前提のはずです。
なのに、大人の決めたルールから外れた「正しくない『行動』」をする、①②③の『考え方』は、④⑤⑥の人々の『行動』を大人が褒めることにより、
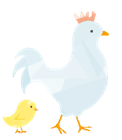
「正しくない『行動』なのだから、良くない『考え方』だ」と、人々に刷り込まれていくわけです。
私たちは、自由に感じ、自由に考えていい
他人と「感じ方」「考え方」が違ってもいい
みんなちがって、みんないい
だから、本当は、『考え方①~⑥』は同等に扱われなくてはなりません。
①②③の『考え方』、誰かに迷惑をかけていますか?
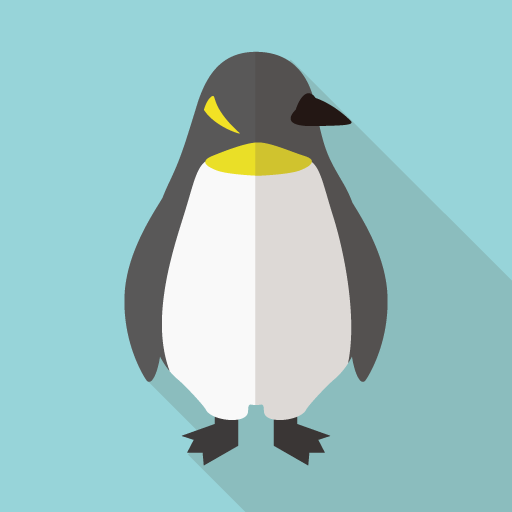
①②③の『考え方』はルールを守らなくて、不快な思いを抱かせる考え方だから、迷惑だぞ!
こう思う人もいます。
しかし…
「①②③は迷惑だ」とするこの思想の人たちが、
「あなたの『考え方』は間違っているからだめだ!」
と言って、①②③を否定し、攻撃する
実は、これが、「他人の自由を奪う」という行為なのです!!
この筆箱ルールで問題なのは、①②③の人々の『行動』です。
「『行動』がルールと合っていない」
ということが問題なのです。
『考え方』については【自由】なのだから、認めることが必要なのです。
それなのに、
「①②③の『考え方』」を否定するというのは、
①②③の人々の【自由】を奪っている、と同じことなのです
自分が正しい、自分が優れている、という思想を持つ人は、自分と違うものについて、否定します。
「自分の『考え方』が正しい」ということは、「自分と違う『考え方』が間違っている」と認識するからです。
他人の『考え方』を認められない。
自分は自分、他人は他人、と分けて考えられない。
自分も他人も、同じ『考え方』、正しい『考え方』をすべきだ!
という思想を持つようになります。
「①②③の『考え方』は迷惑だ」という思想の人々が、
他人の『考え方』を否定する発言となって表れると、「他人の自由を奪う」という行為になってしまう
ということです。
違いを 認める
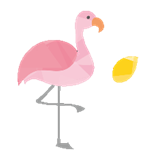
「考え方を同等に扱う」ということを理解するために必要なこと…
それは、「違いを認める」 ということです。
「④の『考え方』の人!そのくらいで先生になんか嫌われないよ!普通はそんなこと思わないのに!」
「③の『考え方』の人!流行にのることなんか気にしなければいいさ!」
「そんな『考え方』をする人は少ないから、あなた、変わってる」
このように思うということは、
「違いを認めることができていない」
ということです。
「私は①の『考え方』だけど、④のように、ルールを守らないことで先生に嫌われちゃうっていうふうに考える人もいるのね」
「私は④の『考え方』だけど、③のように周りと合わせたいという思いが強い人もきっといるでしょう」
「へ~!今までそんな風に考えたことがなかった!そうやって考えることもできるんだね」
自分と異なる他人の心を想像し、認めることができる
自分と異なる考え方を、受け入れることができる

このことができていれば、
「違いを認めることができている」
ということです。
人によって考え方や感じ方が違うというのは、ごく自然なことです。
ところが、
「ルールを守り、大人の言うことを素直に聞いて褒められたから、自分の『考え方』が正しい」と思い込む子供たち
落とし穴にはまってしまった子供たちです。
このまま育つと、「違いを認められない大人」になります。
「自分の『考え方』が正しい(あるいは優れている、普通だ)」と思い、「他の人の『考え方』は間違っているよね」となってしまうのです。
特に、大人から「いい子ね」と褒められて育ってきた、素直でルールに従順な⑥の人たちが、「違いを認められない大人」になります。
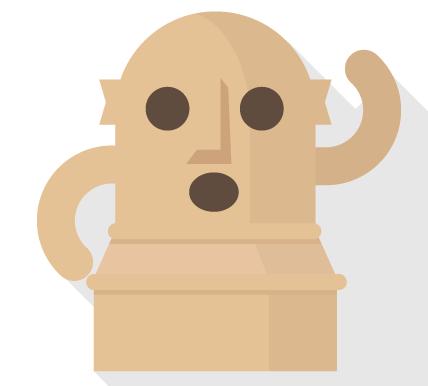
この「違いを認められない大人」
以前の私自身のことを言っています。
私は「いい子ね」と育てられました。
「大人にとって都合がいい」という意味です。
心の中は⑥のような状態です。
「周りの人たちは、正しいことが何で分からないの?」と思っていました。
私は今、自分の身をもって、以前の自分が、
「他人の自由を奪う考え方をしていた」と理解しているのです。
違いを認めることができるようになった時、ようやく自分を客観視できるようになりました。
大切なのは「他人が思っている正しい『行動』をすること」ではありません。
大切なのは「1人1人の 『考え方』『心』」です。
このことを、子育てを通し、我が子に教えられました。
落とし穴に落ちた私は、我が子のおかげで、自分のいた場所から抜け出すことができました。
褒めて育てる…
最近は、「褒めて育てる」という言葉をよく聞きます。
褒めればいいと思って、「大人が正しいと思っている『行動』」ができたときに褒めている大人がとても多いです。
しかし、これは、魂の殺人です。
この行為により、子供は、
『考え方』に優劣をつけるようになります。
違いが認められなくなります。
視点としては、
「自分の考えをもっている」
これが重要なのではないかと、私は考えています
「大人が正しいと思う『行動』ができたとき」
に子供を褒めるのではなく、
「自分の『考え方』を伝え、他人の『考え方』を認めることができたとき」
に子供の成長を喜ぶ。

そうすることで、自己肯定感も高まり、
「自分を表現できる人」
「周りの人々を思いやれる人」
に育っていくのではないかと、
私は考えています。
「自分の考えを持つことができているね!」大人が言葉にしてあげて、一緒に喜ぶ。
「あなたの成長する姿を感じられて、嬉しいよ~♬」というように、大人が自分の感情を表現して喜ぶことで、子供の意欲をどんどん引き出せたら素敵です😊
問題を 解決するために…
では、筆箱ルールについて、この問題とどんな風に向き合えば良いのでしょうか?
いろいろな方法がありますが、私が最も良いと思う方法は、子供がこのことを問題視して話してくれた時に、
「そうだね、いろいろな考え方があるのに、今のルールが合っていないから、問題が起きたんだね」
と、まずは、子供に共感します。
ルールが合っていないことに気付くことができた、そして、自分の考えをもつことができたことを喜びたいです。
子供には、「自分も嬉しい!周りの人も嬉しい!」という感覚を、たくさん味わってもらいたいです。
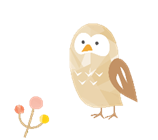
「いろいろな考え方をしている人がいるから、意見をお互いに出し合い、ペンケースについて話し合ってみよう」
と、話し合いの場を設けるのが最善なのではないかと、私は考えています。
互いに様々な意見を聞いて、違いを知る。
互いの考え方、心の中を知り、認め合う。
その上で、一つの策を自分たちで導き出せたら最高だと思います。
自分で決めたことは、自分で守ろうとします。
誰のための ルール?
そもそも、「ペンケースは箱型」というのは誰のためのルールでしょうか?
「子供のため」ですよね。
だけど、
「ペンケースを箱型にする」ということが、本当に子供のためになっているのですか?
1つの価値観の押し付けになっていませんか?
「子供が学習に集中するため」との説明があったけど、ファスナー型だとなぜ集中できないのですか?
鉛筆を削っているかチェックできないから?
高学年で鉛筆を削ったかどうかのチェックは必要?
ついでに言わせてもらうと、鉛筆で書いてると先が丸くなるからイライラして勉強が嫌になっちゃう子もいるのに、なぜシャープペンはダメなの?
大人が鉛筆や箱型のペンケースを使わないのはなぜですか?
高学年になったら、文房具の管理にも慣れて、ファスナー型でも扱えますよね?
大きさが問題だと思うのであれば、そのことについて子供の考えを聞けばいいのでは?
ファスナー型にしたところで、誰かに迷惑をかけていますか?
持ち物がかわいかったり、大好きなものに囲まれてたりしたら、気分が上がって勉強にも力が入りませんか?
鉛筆を一本ずつ差してしまうのは、面倒じゃないですか?
ファスナー型は中身がはっきり分からなくて管理できないし、手紙を潜ませたりしていじめの原因になりかねないから?
もちろん、誰かを深く傷つける取返しのつかないような失敗を防ぐための、大人の確かな目も必要ですけど、ペンケースを箱型にすることで、どれだけいじめを防げるの?
そんなことより、子供の心の叫びやサインを見つけてあげることが、いじめを防ぐ一番の方法なんじゃないのかしら?
子供を信じることで、大人も信じてもらう、という関係も必要なのでは?
最初から禁止しなくても、経験から学ぶことだってたくさんあるのでは?
私は、この筆箱ルールに対し、たくさんの疑問が湧き出てきます。
大人が勝手に、「子供のために箱型が良い」と思っているだけではないでしょうか?
アリストテレス
法律ばかりがたくさんあるのは、悪政の兆候である
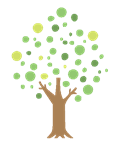
「ペンケースは箱型」というルール、必要ですか?
嬉しい通知♪
文科省 ブラック校則見直し通知
2021/6/11 15:07 配信
▽児童生徒の実情▽保護者の考え方▽地域の状況▽社会の常識▽時代の進展―などを踏まえて校則を見直すよう求めた。
【独自】下着の色指定・特定の髪形禁止…「ブラック校則」見直しを通知 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)
なんと!!
私が学校のルールについて書いているこのタイミングで、文科省が動いてくれました!!
嬉しいです!!
「これが当たり前だ」「自分の時代もそうだった」というような先生に対し、児童生徒が何を言っても「わがまま」にしか聞こえません。
児童生徒が意見を言うのはかなり勇気がいることですし、その意見はほとんど反映されません。
「子供だけで変える」というのは、かなり厳しいです。
こういう権力者(先生)は「自分の『考え方』が正しい」と思っているからです。
違いを認められず、「他の『考え方』」を「良くない『考え方』」と捉えているからです。
下着の色は白だなんて、人権侵害ですよ。
チェックしたり着替えさせたりだなんて、もってのほかです。
若い方ほど、こういう訳の分からない校則や先生の指導について、より身近な問題として感じられるのではないでしょうか。
こういう社会は、「外からの力」「上からの力」が必要です。
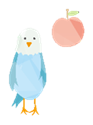
親が、
「このルールは理不尽で、自由がなくて苦しんでいます!変えてくれないなら、しかるべき行動に出ますよ!」くらいの決意で意見を言ったり、
より上位のルールを作っている文科省が、
「あなたのやり方は間違っているからやめなさい!」と言ったりしないと、
変えることは難しいものです。
親や文科省、つまり、
「外からの力」や「上からの力」が必要です
権力者が困るような状況に追い込まないと、変えることができません
文科省で働いている方々、一生懸命働いてくださっているのに、感謝の言葉を受けとる場面が少ないでしょうに…
「これからも、こういうのをどんどん頼みますよ~!」という願いも込めて、「ありがとうございます!!」
読売新聞オンラインの関連記事で、自分たちで議論して学びにつなげた事例をみつけました!
「髪の黒染め訴訟」で流れ変わった「校則」…生徒が議論して歩む「緩和」の道
2021/4/03 09:11 配信
生徒参加で校則議論、学びに活用
「問題意識を持ち、自ら考え、動くことは主体性を伸ばし、周りにも良い影響を与える。誠実に対応したい」
「話し合いを重ねるなかで生徒が論理的に考え、意見を言えるようになった」
「髪の黒染め訴訟」で流れ変わった「校則」…生徒が議論して歩む「緩和」の道 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)
こういう学びの場を設けてくれている学校があることを知り、うれしく思いました!!
もっともっと、小学校、中学校でも、こういう形で考え方の違いを知ることができるような場があるといいな、と思います!!
ストレスや不安・不満の原因
ルールを与えていることによる大きな問題は、子供のストレスや不安・不満の原因となることです。

① かわいいし気分が上がるから、ファスナー型でも良いじゃないの!!
② ファスナー型の方が扱いやすいし、高学年になったら他の子も持ってきているから良いんだよね…
③ 私はルールを守りたい気持ちもあるし、箱型でもいいけど… 流行に乗り遅れたくないから、友達に合わせてファスナー型にしよう。
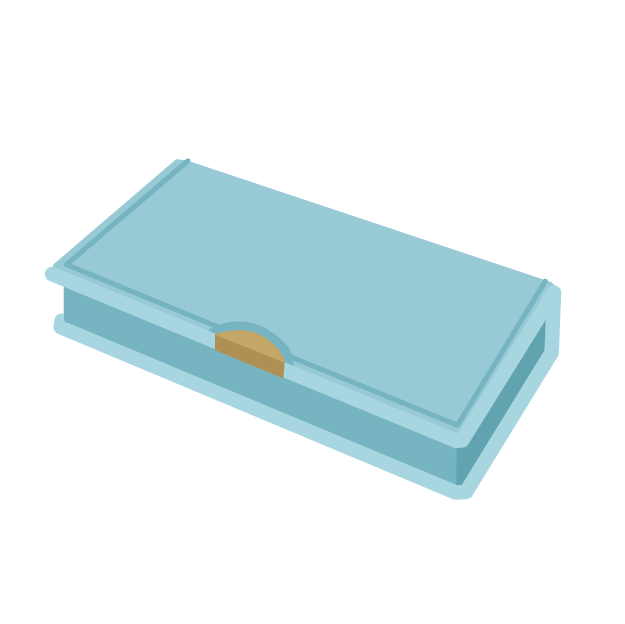
④ 本当は自分だってかわいいファスナー型を使いたいけど、学校がダメって決めてるよ… 大好きな先生を裏切りたくない。
⑤ 箱型だろうがファスナー型だろうが、どうでもいい! 黙ってルールに従っていればいいのに!
⑥ 何でルールを守らないの? ずるい! 私はちゃんと守っているのに! 先生に注意されなければ、ファスナー型にしてもいいとでも思っているの?
このように様々な『考え方』をし、それぞれが最善だと思う『行動』をします。
①の子は、あまり深く考えずに行動するタイプなので、ストレスは少ないです。
(大人に叱られることが多いので、そこではストレスを感じます。)
②の子は、ルールを守っていないことに不安を抱えながら、ファスナー型を使うという行動をとっています。
③の子は、「悪目立ちしたくない」「『普通』でいたい」という思いが強く、人と違うことへの恐怖心があるのだと考えられます。
④の子は、自分の『心』と実際の『行動』が違うためにストレスを抱えます。
⑤の子は、自分の関心がない事柄に周りが騒いでいることを、うっとうしく思っています。
⑥の子は、ルールを守らない人に対する不満が生まれ、ストレスを抱えます。
自分の『考え方』『心』と、自分の『行動』(あるいは他人の『行動』)が異なることにより、ストレスや不安・不満を抱えてしまうのです
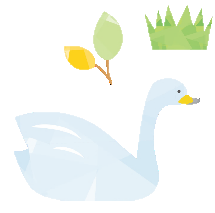
「ペンケースは箱型」というルールを大人が与える。
ルールが実態に合わず、褒めることによって魂の殺人が行われる。
そして、違いを認められなくなる。
さらに、ストレスや不安・不満の原因ともなるのです。
ルールが 実態に合っていたら…
もし、この筆箱ルールが、1人1人の子供の心に寄り添い、子供の実態に合ったものだったら、子供たちはどのように考えるでしょうか。
「自分の持ち物は、自分で選択する」
つまり、自由を奪うルールをなくす、というものです。
子供はこのように考えると想像できます。

① かわいいし、気分が上がるからファスナー型にしよう!!
②ファスナー型の方が扱いやすいし、ファスナー型を使おう!
③ 私は箱型でもいいけど… 友達がファスナー型にしているし、流行に乗り遅れたくない! ファスナー型にしよう!
④ 自分だってかわいいファスナー型を使いたい! 学校がいいって言ってるし、先生もOKだって!
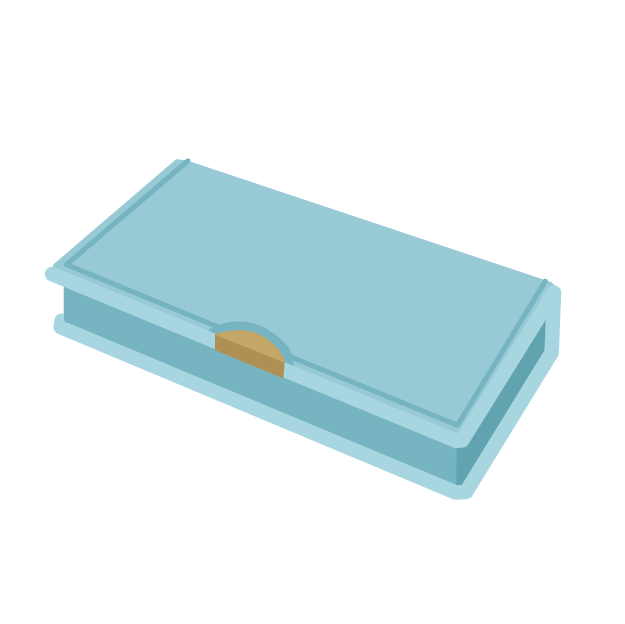
⑤ 箱型だろうがファスナー型だろうが、どうでもいい! 私は箱型のままで別にいいや。
⑥ みんなルールを守っているね! 私もみんなもルールを守っている。
どの子も、自分の『考え方』の通りに『行動』に移すことができます。
『考え方』と『行動』が一致するので、ストレスや不安・不満を抱えません。
「自由を奪うルールを与えない」
このことで、心も穏やかになれるのです
「自分で選択できる」
これが、1人1人が大事にされるシステムです
そして、大人が褒めるという魂の殺人が行われないため、「この『考え方』が正しい」というのもなくなります。
⑥の『考え方』の子は、「ルールを守って偉いね」と大人から褒められないので、「自分の『考え方』が素晴らしい」となりません。
⑥の『考え方』の子は、①②③の『考え方』の子供たちに対しても、「ルールを守っている」「正しい『行動』をしている」と認識し、考え方の違いも認められるようになります。
「ルールとして望ましい『行動』を示す」ということが、どれだけの混乱を招くことか…
「実態に合っていないルールを与える」ということが、どれだけ深く子供の心に影響があることか…
ルールを守っている子供を褒める「魂の殺人」が、どれだけ多くの子供たちの心を壊していることか…
『行動』を示すルールは、本当に必要なものに精選しておくことが必要です。
その時の子供たちの実態に合ったものに「変えていくこと」が大事です。
違いを認め合えるようになることが、1人1人の幸せにつながっていきます。
従順という心の病い
アルノ・グリューン 著
~私たちはすでに従順になっている~
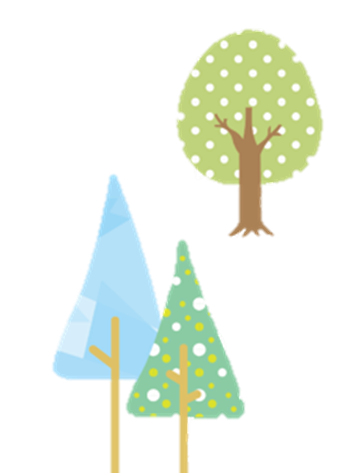
大人自身も「ルールに従って『行動』するのが良いことだ」いう刷り込みのもと、従順に育ってきた方が多いのではないかと思います。
そして、ルールを与えられたり、望ましい行動を示されたりしたことで、いろいろな思いを抱き、ストレスや不安・不満を抱えてきた方も多いのではないでしょうか。
そういう経験をされている方であれば、なおさら、
次の世代には、「我慢を強いるような、苦しい思いをさせたくない!」という思いで、
ルールや教育方法を変えることができる。
周りの人々の『心』に寄り添うことができる。
私はそう思っています。
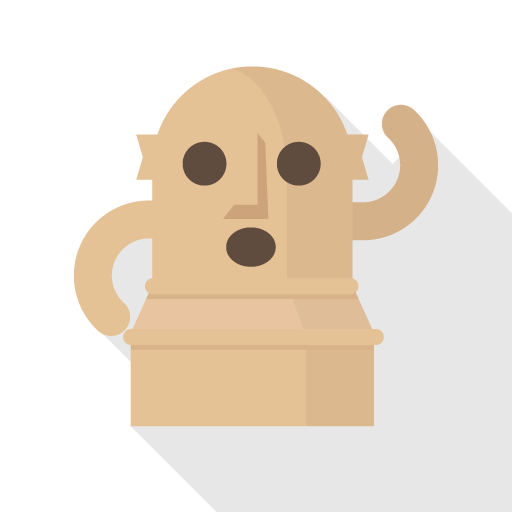
実は、私たちが手にしているのは、【自由】の【権利】だけです
まだ手に入れていない自由はたくさんあるのです!!
多くの方々に自由を謳歌してほしい!
子供たちにも自由をプレゼントしたい!
そういう思いで、この文章を書いています!!
人生に必要な知恵はすべて幼稚園の砂場で学んだ
ロバート・フルガム 著
小学校も、人生に必要な知恵を学ぶ場所です。
多くの大人は(少なくとも私の世代は)、小学校、中学校などで筆箱ルールのようなことを議論したり、考え方の違いについて学んだりしてこなかったように思います。
必要なこと、大切なことを学べていない大人が多いのではないでしょうか。
私自身、ほとんど議論を経験していません。
だから、それがそのまま今の日本社会になっていて、今の法律が当たり前の社会になり、心の歪みに気付かずに、放置されているのかもしれません。
ルールを守っている人と、守っていない人、それぞれの心に歪みが生じます。
①~⑥のように、いろいろな考え方を想像し、当てはめてみると、いい解決策がみつかるかもしれないですね!
ただ、著作権問題については「筆箱ルール」と、ちょっと違います。
著作権を考えるときに気を付けなくてはいけないのは、制作者を守るためのものが著作権だということです。
私たちが認められているのは、
「人の迷惑にならない限り、【自由】に表現してよい」
ということです。
大事な作品の世界を壊されたら、それは、「迷惑」になるわけです。
①~⑥の、私たち視聴者の『考え方』だけでなく、大事な大事な制作者の『考え方』というものをプラスして考えなければなりません。
「権利を守るルール」は、人々の幸せを守るために必要です。
「自由を奪うルール」は、心の歪みのもとです。
「自由を奪うルール」をなくすことで、ストレスや不安の解消につながります。
いろんな考え方をする人たちの心に寄り添い、互いに違いを認め合うことができたら、ストレスや不安は軽減されます。
私たちは、自由に考え、自由に感じて、良いのです!!
みんなで自由を謳歌し、幸せになりましょう!
子供たちに、自由をプレゼントしましょう!
マイノリティ(少数派)の人も、マジョリティ(多数派)の人も、
ストレスや不安を抱えることなく、
自由に生きられる世の中になりますように!!!
私は強く願っています!

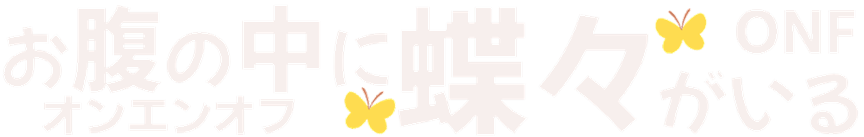
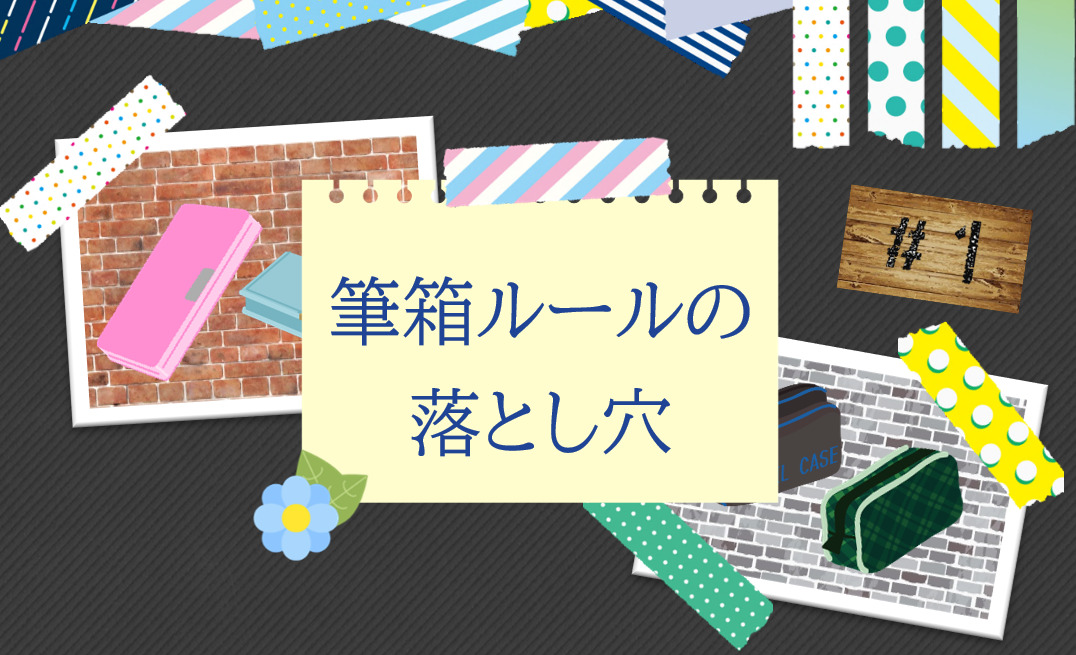


① かわいいし気分が上がるから、ファスナー型でも良いじゃないの!!
② ファスナー型の方が扱いやすいし、高学年になったら他の子も持ってきているから良いんだよね…。
③ 私はルールを守りたい気持ちもあるし、箱型でもいいけど… 流行に乗り遅れたくないから、友達に合わせてファスナー型にしよう。